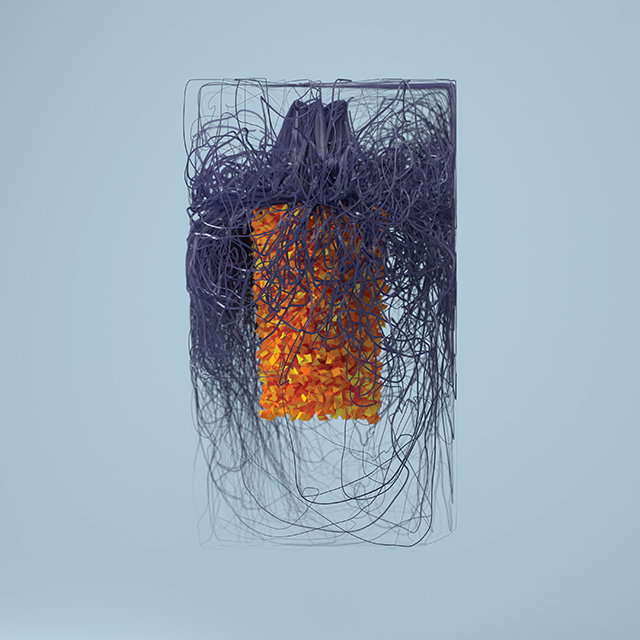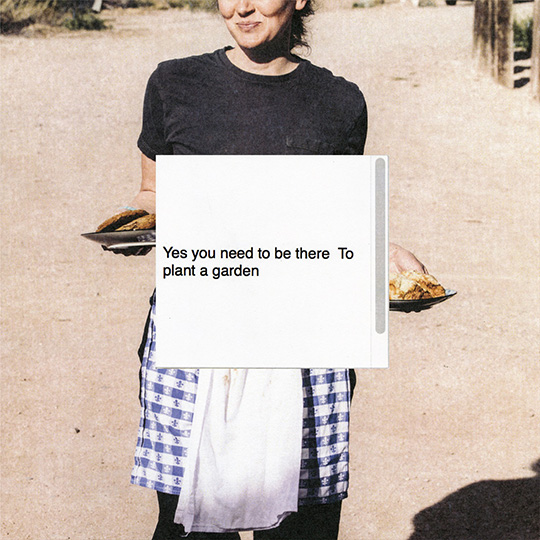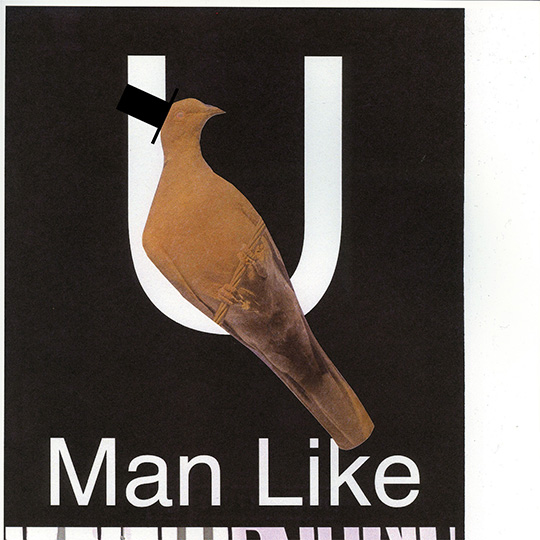これは爆弾かもしれない。ダークなエレクトロニック・サウンドを響かせる中国四川省は成都の6人組、その名もストールン(秘密行動)が8月7日に日本デビュー・アルバム『Fragment』をリリースする。彼らの楽曲はニューウェイヴ~ゴシック~シンセ・ポップなど、間違いなく英米ロックから影響を受けているが(10月からはニュー・オーダーのツアーに同行することも決定しているそう)、音楽については保守的で厳しいという中国において、なぜこのようなバンドが登場するに至ったのか? ワーキングクラス出身のフロントマン、リャン・イーによれば、まず海賊盤でポーティスヘッドやジョイ・ディヴィジョンと出会い、その後ネット経由でさまざまな海外の音楽にアクセスしていったのだという。なかでもクラフトワークの存在は大きかったようで、借金までしてライヴを観に行ったのだとか(そのあたりの経緯はHEAPの記事に詳しい)。気になる点はまだまだ多いが、いまは続報を待とう。
[7月5日追記]
本日、8月リリースのアルバムより収録曲“Chaos”が先行配信された。またなんと、同曲の石野卓球によるリミックスも公開、同氏からはコメントも届いている。「このダイナミックなトラックをリミックスできて光栄です。楽しくできました」とのこと。配信はこちらから。
STOLEN
ダークでミステリアスな、テクノとロックのミクスチャー・サウンドが、ヨーロッパのアンダーグラウンド・シーンで注目を集める、中国のインディーズ・バンド“STOLEN(ストールン)”が、今年8月、日本でデビュー・アルバム『Fragment(フラグメント)』をリリースすることが決定しました。
“STOLEN(漢字表記では“秘密行動”)”は、中国で今最も刺激的な音楽シーンのひとつとして知られる四川省の省都・成都(せいと)を拠点に活動する、平均年齢26歳の5人の中国人と1人のフランス人で構成されるバンドです。
STOLEN Trailer for Japan
https://youtu.be/eeEbvS1hsYY
プロデューサーは、イギリス、マンチェスター生まれの音楽プロデューサー、ミュージシャンである、Mark Reeder(マーク・リーダー)。
マーク・リーダーは、70年代当時、ジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスや、マッドチェスター・ムーヴメントを巻き起こした〈ファクトリー・レコード〉のオーナーでナイトクラブ「Hacienda(ハシエンダ)」の創始者、トニー・ウィルソンと親交の厚かった人物。ニュー・オーダーにも多大な音楽的影響を与えており、マーク・リーダーの存在がなければ、ニュー・オーダーの名曲“Blue Monday”も生まれることはなかったと言われています。
また1990年にベルリンで立ち上げた音楽レーベル〈MFS〉は、ポール・ヴァン・ダイクや、エレン・エイリアンら世界的なスターDJを輩出した伝説的エレクトロニック・ミュージック・レーベルとして知られていますが、実は、電気グルーヴの作品を初めてヨーロッパへ向けてリリース(1995年のヒットシングル「虹」をリリース)したレーベルであり、マーク・リーダーは、電気グルーヴと石野卓球氏がその後ヨーロッパでのキャリアを築くきっかけを作った重要人物でもあります。
STOLEN を中国で見出したマーク・リーダーは「ニュー・オーダー以来の衝撃を受けた」と語り、2007年に活動を停止していた〈MFS〉レーベルを再び活性化することを決意、STOLEN のデビュー・アルバム『Fragment』をプロデューサーとして完成させました。
日本では今年8月に、アルバムをリリースすることが決定。マーク・リーダーと石野卓球氏のリミックス音源を含む全13曲を収録したアルバム『Fragment』を〈U/M/A/A〉よりリリースします。
また、STOLEN は10月にスタートする、ニュー・オーダーのライヴ・ツアーに、スペシャル・ゲストとして参加することも決定しています。アルバムのリリースに先駆け、先行配信なども行う予定。今後の動向にご注目ください。

【Stolen プロフィール】
中国で今最も刺激的な音楽シーンのひとつと言われる、四川省の省都・成都(せいと)を拠点にする平均年齢26歳の5人の中国人と1人のフランス人で構成される6人組のインディーズ・バンド。2011年結成。バンド名「STOLEN(ストールン、漢字表記は秘密行動)」は、神秘的、秘密主義、暗やみなどを意味する。
インディーズ・バンドとして中国国内での数多くのライヴ・ツアーを積み重ねた後、2016年に初めての海外ライヴとしてフランス《Trans Musicales Festival》に出演、2017年、フランス《SAKIFO Music Festival》に出演、2019年にはアメリカ SXSW に招かれるがビザの問題で入国することが許されなかった。
謎多き中国のインディーズ・シーンから全世界デビュー・アルバムとなる『Fragment(フラグメント)』はドイツ・ベルリンの伝説的レーベル〈MFS〉のオーナー Mark Reeder がプロデューサーとなり、成都にある彼らのホームスタジオとベルリンのスタジオでレコーディングされた。テクノやロックといったカルチャーを独自に吸収したそのサウンドやライヴ・ステージ、アートワークは、中国の若者から人気を集めるポストロック~ダークウェイヴの旗手として、その注目は世界中へと拡がっている。
【バンド・メンバー】
Vocals / Synth : Liangyi
Guitar / Keyboard / Samples / Vocals : Duanxuan
Guitar / Vocals : Fangde
Bass : Wu Junyang
Drums, Percussion : Yuan Yufeng
VJ : Formol
【Stolen SNS】
Weibo: https://www.weibo.com/mimixingdong
Instagram: https://www.instagram.com/stolen_official/
Facebook:https://www.facebook.com/strangeoldentertainment/