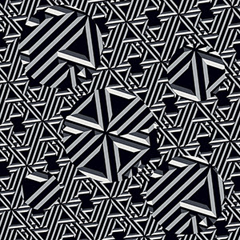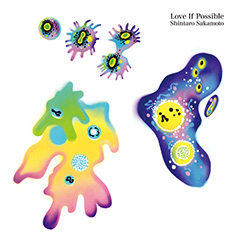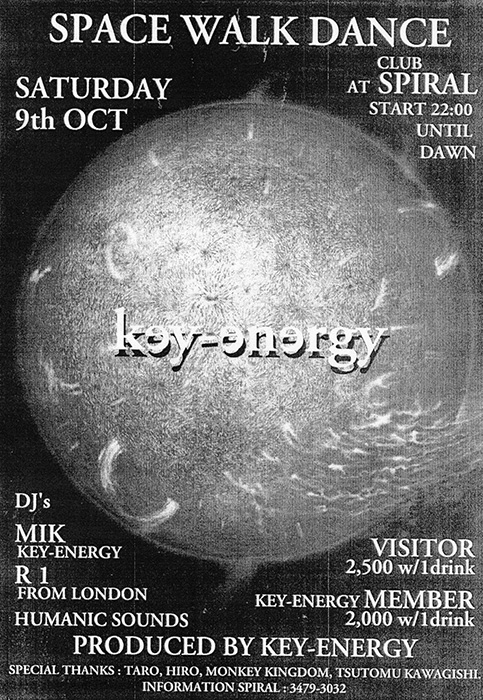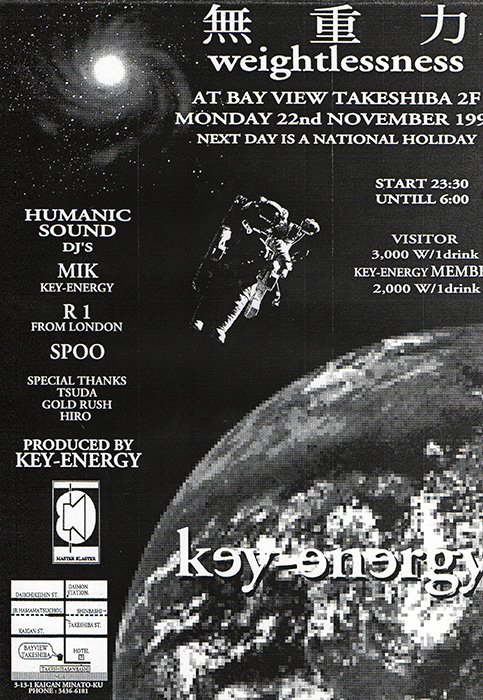日本を代表するプロデューサー、ゴス・トラッドが新作『PSIONICS(サイオニクス)』を自身のレーベル〈Back To Chill〉よりリリースする。ここ数年の間に、マーラ主宰の〈Deep Medi Musik〉や〈Back To Chill〉から楽曲を発表してきたゴス・トラッドだが、アルバムという形でのリリースは前作『New Epoch』から実に4年ぶり。
前作がゴス・トラッドのダブステップ期を総括しているものだとしたら、新作『PSIONICS』は、よりフリーフォームで重低音を追求し続ける近年の彼の活動が反映されたものになっている。今回収録される曲の多くが使用されたこちらのミックスは、彼のキャリア初期を彷彿とさせるドローン・サウンドから、彼のスタイルとも深く共鳴するドゥーム・メタル、メランコリックなメロディで溢れている。アルバムへの期待が高まる内容だ。
今作は販売形式もユニークで、値段に応じて内容が異なる仕様になっている。ゴス・トラッド自身が自らのDJプレイで使用するレコードを制作しているスタジオ、ワックス・アルケミー製の高品質ダブプレートが入ったパッケージもあるので、彼のサウンドへの美学に「触れる」貴重な機会になるだろう。こちらのダブプレートには日本のバンド、ボリスやアメリカのエクペリメンタルMC、Dälekとの曲作などが収録される。
発売は9月上旬を予定。同月には今年10周年を迎えるゴス・トラッドのパーティ〈Back To Chill〉のアニヴァーサリー・イベントも行われる。
Artist: Gpth-Trad
Title: PSIONICS
Label: Back To Chill
Track List (変更の可能性あり):
01. Grind *
02. Vortex *
03. Amazon *
04. Locomotive * 05. Eraser *
06. Crooked Temple 07. Disorder *
08. One Drop *
09. Joust *
10. Untitled
* VIPパッケージの4枚組ダブプレートに収録予定の8曲
予約はこちらから: https://www.gothtrad.com/psionics/