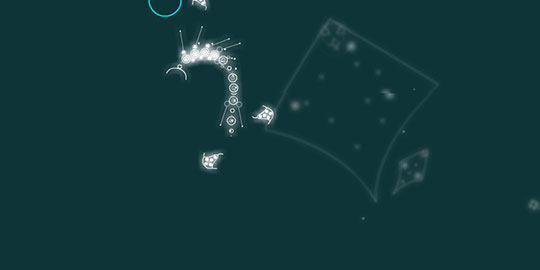これよりいい音楽作品はたくさんある。なんてことをアレクシス・テイラーは自分から言わないかもしれないが、すくなくとも、ホット・チップと離れたところで彼が発表するプロジェクトに共通してうかがえるのは、世の完成された音楽とのあいだに距離をおきくかのように、自らの作品に未完成性を残したまま発表するような姿勢だ。彼の以前のソロ作『ラブド・アウト』はGarageBandを用いてつくられたさしずめホーム・デモ集だった。ジョン・コクソン(スピリチュアライズド/スプリング・ヒール・ジャック)/パット・トーマス/チャールズ・ヘイワード(ディス・ヒート)との連名作『アバウト』は一堂の会したその日のジャムで、同メンバーの2作目にあたるアバウト・グループによる『スタート & コンプリート』はスタジオ入りの数日前に聴かせたデモ音源をもとに1日で録音されたプリプロ段階のような半即興アルバムだ。いずれも、ホット・チップのようにプロダクションを作り込む、ということを避けている。
なぜアレクシスは未完成性を作品に残すのか。
おそらく、彼は気持ちのどこかで引っ込み思案になっているのではないかと思う。グッド・ミュージックへのコンプレックスめいた葛藤とでも言えるだろうか。
アレクシスにはミュージシャンであるのと同じかそれ以上にオタクなまでにリスナー気質があるように思える。自分の音楽趣味を歌うことがよくあるし("ダウン・ウィズ・プリンス")、ミュージシャンである自分を俯瞰さえした歌詞もある("フルーツ")。インタヴューでも好きな音楽に関して雄弁になっていることが多い。世にいい音楽がたくさんあることを知っていて、そのなかであえて自分が音楽を作って世に送りだすとき、たとえそれがオリジナルなものであると自信を持っていようと、他人が自分の作品をよしとするかどうかに期待がないのだろう。未完成性を残すのは、グッド・ミュージックで満ちあふれる世の中あるいは(ホット・チップが活動してきた)メジャー・フィールドからの、アレクシスなりの降り方なのではないか。そして、そうしたある種のプレッシャーから自由になれる彼の居場所が、自宅にあるという音楽部屋なのだろう。ひとりの作業で、自らの内に内にこだわりをもって向かっていく。ビートルズやビーチ・ボーイズのようなオールディーズのレア音源(ブートレグ)を彼は多く所有しているし、ホーム・デモや初期テイクの演奏の質感への憧憬もあるかもしれない。
今作『ナイム・フロム・ザ・ハーフウェイ・ライン』は、とにかく全4曲とも、アレクシスなりの音や楽器へのフェティッシュなこだわりがうかがえる。というか、おそらくそれだけのために作られている。
反復するリズムボックスのうえから、"ローズ・ドリーム"なんて曲もあるようにローズを得意気に弾きながらも、ぎこちないベースを弾いてみせたり、ワウをかけまくった(おそらく)ギターの音や、風呂場で録ったようなドラム/パーカッションのやはりぎこちない音が披露される。4曲中3曲で聴かれるドラム/パーカッションは、特にフェティッシュな響きを曲に与えていて、ぎこちなさが楽器へのこだわりそのものを際立たせている。それらが挟まれるタイミングが、彼の親友であるブライアン・ディグロー(ギャング・ギャング・ダンス)のカットアップと似た響きをもっているのも微笑ましい。
逆に、アレクシスの最大の魅力である歌声があまり聴かれないのも、楽器への偏重を物語る。ヴォーカルが入っていても、それはピッチ操作をされていたり、ロボ声に取って代わられていたりする。少ない言葉のリフレイン、無感情のヴォーカルなど、今作はいささか挑発的でひねくれた感覚があり、これまでの彼が披露してきた魅力を自ら封じているのは明らかだ。クリスマスに録音されたという"ジーザス・バースデイ"にいたってはまったくのインストで、エコーとディレイがかった微細なノイズが間隔を空けながらも情感的に鳴らされる。外のことを忘れ、音楽部屋にこもりきり、ひとりでこれを作っているアレクシスの姿を容易く思い浮かべられる。誰の理解をも求めないフェティシズム、ここに極まれり。
しかし、そのフェティシズムはどこからくるのか。
アレクシスは音楽部屋にこもりながらも、間違ってもトクマル・シューゴのような楽器の名手というわけではない。ドラムが苦手だと僕に話してくれたこともあれば、本誌インタヴューではギターがまったく下手で、ナチュラルに弾けないと答えている。が、しかし、そのふたつは今作でも目立って聴こえる楽器だ。
以前、アレクシスといっしょにオーネスト・ジョンズに行ったとき、おすすめを尋ねたところ、オマー・ソウリーマンとグループ・ドゥウェイで、そのころのアレクシスのギターのエフェクトはこの両者のサウンドとよく似ていた。
今作『NFTHL』についての『ディス・イズ・ザ・フェイクDIY』誌でのインタヴューでは、彼の大好きなロイヤル・トラックスのギタリストの名をあげている。アレクシスは、自らの音楽ヒーローへの憧れ(あるいはワナビズム)と不得意の狭間で楽器を演奏しているのかもしれない。そうだとすればこそ、その狭間で生じるやりきれなさや、憧れが背後にあるフェティシズムが、未完成性をともなった作品としてレコードに着地してしまうのではないだろうか。
いずれにせよ、昨年のホット・チップのようなポップネスや完成性を今作に求めてもいけないし、アバウト・グループのような歌心も期待してはいけない。あくまでリスナーにできるのは、決して雄弁になれないもどかしさのつきまとう楽器演奏をあたたかく見守ることだけだ。
残る疑問として、なぜこのタイトルなのか。昨年のホット・チップ来日公演でもオリンピックのマークを模したTシャツを着ていたし、フットボールネタが熱かったのだろう。ロンドンのフットボール・チームであるアーセナルとトッテナムの確執が念頭にあるようだが、アイロニーをこめているのかも不明瞭である。
参照記事
トッテナムがアーセナルを嫌いな理由 - Fun!!Footba!! -:
https://shamoonyouspurs.blog118.fc2.com/blog-entry-73.html
Alexis Taylor: 'I Can Make More Enjoyable Mistakes On My Own' | Features | DIY:
https://www.thisisfakediy.co.uk/articles/features/alexis-taylor-i-can-make-more-enjoyable-mistakes-on-my-own/
interview with Hot Chip - いいですか? 絶対に真実は言わないください | ホット・チップ | ele-king:
https://www.ele-king.net/interviews/002235/
さあ、世界よ、グッドメロディのポップ・ソングをもって小躍りせよ―ホット・チップが新作『イン・アワー・ヘッズ』を発表&来日! | Qetic - 時代に口髭を生やすウェブマガジン "けてぃっく":
https://www.qetic.jp/interview/hot-chip/80557/












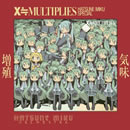


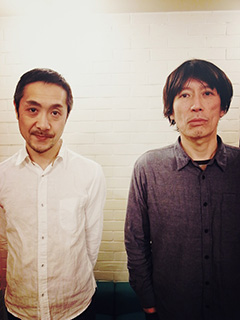 森俊二(Natural Calamity)と石井マサユキ(Tica)の二人によって2000年に結成されたギター・インストゥルメンタル・ユニット。2004年にファースト・アルバム『Straw Hat, 30 Seeds』を発表。続いて2006年に発表したセカンド・アルバム『Nicky's Dream』はその年のベスト・アルバムとして多くのメディアで取り上げられた。同アルバムからの楽曲は、様々なコンピレーションや映画『ホノカアボーイ』のサウンドトラックにも収録。2012年4月には渾身のサード・アルバム『Twilight For 9th Street』をリリースした。また、トリップ感溢れるライヴ・パフォーマンスも各方面で絶賛され、これまでにFUJI ROCK FESTIVAL、GREENROOM FESTIVAL、Sense of Wonder、SUNSET LIVEなどの大型フェスへも出演を果たしている。
森俊二(Natural Calamity)と石井マサユキ(Tica)の二人によって2000年に結成されたギター・インストゥルメンタル・ユニット。2004年にファースト・アルバム『Straw Hat, 30 Seeds』を発表。続いて2006年に発表したセカンド・アルバム『Nicky's Dream』はその年のベスト・アルバムとして多くのメディアで取り上げられた。同アルバムからの楽曲は、様々なコンピレーションや映画『ホノカアボーイ』のサウンドトラックにも収録。2012年4月には渾身のサード・アルバム『Twilight For 9th Street』をリリースした。また、トリップ感溢れるライヴ・パフォーマンスも各方面で絶賛され、これまでにFUJI ROCK FESTIVAL、GREENROOM FESTIVAL、Sense of Wonder、SUNSET LIVEなどの大型フェスへも出演を果たしている。 ハワイで生を受け、2歳の時に日本へと移住。中高時代はパンクやオルタナに開眼し、ハイティーンの頃には友人のユタカ、Delawareの点、そして立花ハジメとLow Powersのメンバーでもあったエリと、携帯電話の着信音をオケに使用し歌うというユニークなバンド、The Japaneseを結成し活動した。そしてボルティモアに渡った後、マット・パピッチとエクスタティック・サンシャインの活動を始める。同時に彼は通っていた美術大学のクラスメート達と共にポニーテイルを結成。カオティックなサウンドと怒濤のライヴ・パフォーマンスは瞬く間に話題となる。また、エクスタティック・サンシャインとしても〈カーパーク〉からデビュー・アルバムをリリースし、多方面から高評価を得るもののダスティンは脱退する。ポニーテイルもさらなるブレイクを期待されていたが突然活動休止を発表(2011/9/22に解散を発表)。そしてダスティンは〈スリル・ジョッキー〉と契約し、サード・ソロ・アルバムをリリースした。多数のエフェクターを足元にならべ、ディレイ、ループ等を駆使し、ミニマルでカラフルなレイヤーを描き出していくギター・パフォーマンスは注目を集めている。2012年通算4作目となるアルバムをリリースし、4月にはレコード発売記念の日本ツアーも敢行。NHKライヴ・ビートへの出演も果たす。7月にはNYで行われたダーティー・プロジェクターズの最新作のリリース記念ライヴのオープニングに抜擢され、10月の日本ツアーでも全公演オープニングを務めた。9月から10月前半にかけてビーチ・ハウスとのUSツアーを行った後、朝霧JAM2012にも出演を果たした。
ハワイで生を受け、2歳の時に日本へと移住。中高時代はパンクやオルタナに開眼し、ハイティーンの頃には友人のユタカ、Delawareの点、そして立花ハジメとLow Powersのメンバーでもあったエリと、携帯電話の着信音をオケに使用し歌うというユニークなバンド、The Japaneseを結成し活動した。そしてボルティモアに渡った後、マット・パピッチとエクスタティック・サンシャインの活動を始める。同時に彼は通っていた美術大学のクラスメート達と共にポニーテイルを結成。カオティックなサウンドと怒濤のライヴ・パフォーマンスは瞬く間に話題となる。また、エクスタティック・サンシャインとしても〈カーパーク〉からデビュー・アルバムをリリースし、多方面から高評価を得るもののダスティンは脱退する。ポニーテイルもさらなるブレイクを期待されていたが突然活動休止を発表(2011/9/22に解散を発表)。そしてダスティンは〈スリル・ジョッキー〉と契約し、サード・ソロ・アルバムをリリースした。多数のエフェクターを足元にならべ、ディレイ、ループ等を駆使し、ミニマルでカラフルなレイヤーを描き出していくギター・パフォーマンスは注目を集めている。2012年通算4作目となるアルバムをリリースし、4月にはレコード発売記念の日本ツアーも敢行。NHKライヴ・ビートへの出演も果たす。7月にはNYで行われたダーティー・プロジェクターズの最新作のリリース記念ライヴのオープニングに抜擢され、10月の日本ツアーでも全公演オープニングを務めた。9月から10月前半にかけてビーチ・ハウスとのUSツアーを行った後、朝霧JAM2012にも出演を果たした。 エレクトロニクスと生楽器を絶妙なバランスで調和させ、力強さと繊細さを自然体で同居させる。湘南・藤沢を拠点に活動を続け、人間味溢れる温かいサウンドを志向するアーティスト、鎌田裕樹による電子音楽団tickles(ティックルズ)。2006年発売のファースト・アルバム『a cinema for ears』リリース後から続けてきたバルセロナやローマ、韓国などを巡ったライブ・ツアーでは、人力の生演奏を取り入れたスリリングでドラマチックなライブ・パフォーマンスで大きな賞賛を得た。そんな数々の経験を経て紡がれた珠玉の楽曲をたっぷりと詰め込んだ待望のセカンド・アルバム『today the sky is blue and has a spectacular view』(2008年)は自身のレーベル〈madagascar(マダガスカル)〉よりリリースされ、TOWER RECORDS、iTunesを中心にセールスを伸ばし、高い評価を得た。2011年、次なるステップへと進むべく〈MOTION±〉と契約。ピアノ、シンセサイザー、フェンダー・ローズ、ピアニカ、オルガン、鉄琴、オルゴール、ギター、ベースなど、様々な楽器を駆使しながら感情的なメロディーと心地良いリズムを生み出していくスタイルに更なる磨きをかけ、2012年4月にニュー・アルバム『on an endless railway track』をリリース。6月にはSchool of Seven Bells来日公演のサポート・アクトを務めるなど、リリース後はエレクトロニクスとリアルタイム・サンプリングを駆使するライブ活動を精力的に展開。柔らかいビートの上で胸を震わせる旋律が幾重にも重なり合い、交錯していく夢幻のサウンドスケープは、聴く者の心を捉えて離さない。
エレクトロニクスと生楽器を絶妙なバランスで調和させ、力強さと繊細さを自然体で同居させる。湘南・藤沢を拠点に活動を続け、人間味溢れる温かいサウンドを志向するアーティスト、鎌田裕樹による電子音楽団tickles(ティックルズ)。2006年発売のファースト・アルバム『a cinema for ears』リリース後から続けてきたバルセロナやローマ、韓国などを巡ったライブ・ツアーでは、人力の生演奏を取り入れたスリリングでドラマチックなライブ・パフォーマンスで大きな賞賛を得た。そんな数々の経験を経て紡がれた珠玉の楽曲をたっぷりと詰め込んだ待望のセカンド・アルバム『today the sky is blue and has a spectacular view』(2008年)は自身のレーベル〈madagascar(マダガスカル)〉よりリリースされ、TOWER RECORDS、iTunesを中心にセールスを伸ばし、高い評価を得た。2011年、次なるステップへと進むべく〈MOTION±〉と契約。ピアノ、シンセサイザー、フェンダー・ローズ、ピアニカ、オルガン、鉄琴、オルゴール、ギター、ベースなど、様々な楽器を駆使しながら感情的なメロディーと心地良いリズムを生み出していくスタイルに更なる磨きをかけ、2012年4月にニュー・アルバム『on an endless railway track』をリリース。6月にはSchool of Seven Bells来日公演のサポート・アクトを務めるなど、リリース後はエレクトロニクスとリアルタイム・サンプリングを駆使するライブ活動を精力的に展開。柔らかいビートの上で胸を震わせる旋律が幾重にも重なり合い、交錯していく夢幻のサウンドスケープは、聴く者の心を捉えて離さない。 クラブのみならず、ファッションショーやホテル、ショップ、カフェなど、およそ音楽と触れ合うことが出来る空間すべてに良質な選曲を提供してきた山崎真央(gm projects / AKICHI RECORDS)、鶴谷聡平(NEWPORT)、青野賢一(BEAMS RECORDS)の3人の頭文字を並べて命名されたユニット「真っ青」。20年以上のDJキャリアに裏付けされたスキル、レコード・CDショップのバイヤー経験がもたらす豊潤な音楽的バックグラウンド、そしてアート、文学、映画などにも精通する卓越したセンスから生まれるそのサウンドは、過去、現在、未来に連なる様々な心情を呼び起こし、聴くものの目前に景色を描き出すものである。リミックスを手掛けた「中島ノブユキ/Thinking Of You (真っ青Remix)」 はまさに青いサウンドスケープ。
クラブのみならず、ファッションショーやホテル、ショップ、カフェなど、およそ音楽と触れ合うことが出来る空間すべてに良質な選曲を提供してきた山崎真央(gm projects / AKICHI RECORDS)、鶴谷聡平(NEWPORT)、青野賢一(BEAMS RECORDS)の3人の頭文字を並べて命名されたユニット「真っ青」。20年以上のDJキャリアに裏付けされたスキル、レコード・CDショップのバイヤー経験がもたらす豊潤な音楽的バックグラウンド、そしてアート、文学、映画などにも精通する卓越したセンスから生まれるそのサウンドは、過去、現在、未来に連なる様々な心情を呼び起こし、聴くものの目前に景色を描き出すものである。リミックスを手掛けた「中島ノブユキ/Thinking Of You (真っ青Remix)」 はまさに青いサウンドスケープ。