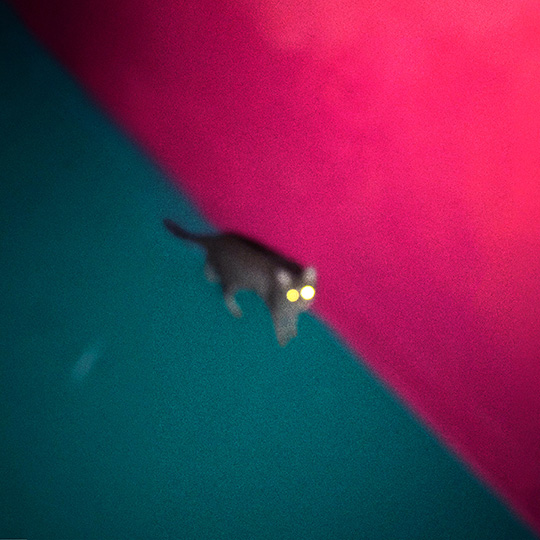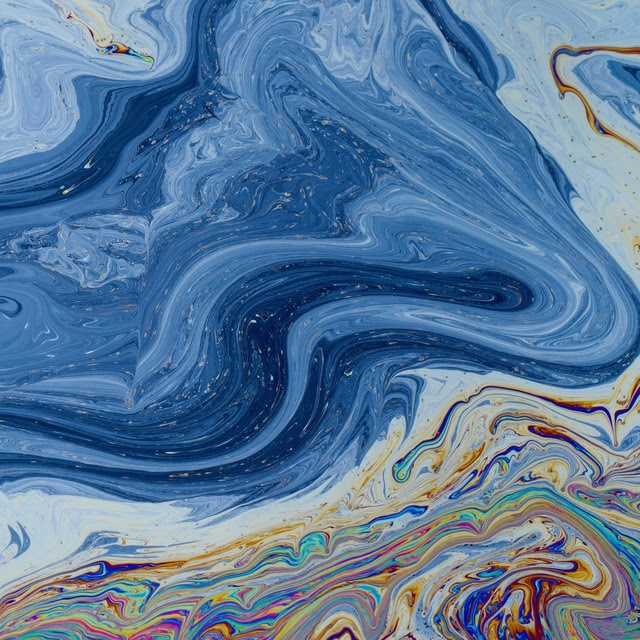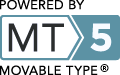ぶん殴る。それがタイトル『Wallop』の意味だ。直球である。アティテュードにかんしていえば当時のニューヨーク市長、ジュリアーニを痛烈に批判した2003年の出世作「Me And Giuliani Down By The School Yard (A True Story)」のころから何も変わっていない。
とはいえもちろん、チック・チック・チックはもう20年以上活動を続けているバンドである。細部のサウンドは幾度も変化を重ねてきた。もろにディスコに傾斜した前作『Shake The Shudder』から2年、今回の新作はだいぶヴァラエティに富んだ内容に仕上がっている。不穏でいかめしげな1曲目から、アコースティックなギターとエディットされた音声のかけ合いが最高の快楽をもたらすハウス調の“Couldn't Have Known”を経て、先行シングル曲“Off The Grid”へといたる序盤の流れや、80年代の歌謡曲のような主旋律とアレンジに、それとは正反対の強烈なドラムスが覆いかぶさる“Serbia Drums”もおもしろいのだけれど、このアルバムの醍醐味はそれ以降の展開にある。もの憂げな“Slow Motion”も新鮮だし、「5万ドルでは俺の心は変えられない」と歌われる“$50 Million”では、ベースがなんとも不思議な動きを見せている。あるいは、チャイルディッシュな電子音が特徴の“Domino”も、チック流ダーク・エレクトロを聴かせる“Rhythm Of The Gravity”も、ともに加工された音声が印象的で、いつもとはちょっと異なる彼らの表情を垣間見させてくれる。1枚のなかにこれほどさまざまなアプローチが同居しているのは、彼ら史上初めてのことではないだろうか。
それら種々の試みすべてに共通しているのはそして、やはりダンスである。どれほど細部に趣向を凝らそうとも、彼らがダンスを忘れることは絶対にない。どんなに社会や政治の状況が絶望的であろうとも、彼らは踊り狂うことでそれを笑い飛ばす。それこそがチック・チック・チックというバンドの本懐であり、また今回の「ぶん殴る」という「反撃」の支柱でもあるのだろう。どこまでもほとばしる熱いパッション……いやはや、秋の来日公演が楽しみでしかたない。
前回の大統領選挙では、共和党からびっくりするようなパンチをくらった気がした。このアルバムは俺たちの反撃を意味している。俺たちもやつらにたいして「Wallop」をお見舞いしたいと思ったんだ。
■今回の新作のアートワークでは、ネコが目を光らせて境界を渡っています。これは、ネコはヒトが決めた境界を軽々と越えていく、というようなメッセージなのでしょうか?
ニック・オファー(Nic Offer、以下NC):(笑)。そうじゃないけれど、その解釈は最高だね。俺のお隣さんが引っ越して出ていったんだけど、俺はその部屋の開け方を知っていたからドアを開けて入った。俺はパーシーという名の子猫を飼っていて、パーシーは基本的には俺の家の部屋という世界しかいままで知らなかった。そのとき、パーシーも隣の家に入ってきて、突然パーシーにまったく新しい世界が開けた。パーシーはとても昂奮して、全神経を研ぎ澄ましていたよ。パーシーが隣のアパートメントに入ったところの瞬間の写真を撮ったんだ。アートを作るとき、俺はそういう感覚でいたい。まったく新しい世界に入り込んだ子猫のような感覚。
■ちなみに、ネコ好きですか?
NC:(笑)。好きかどうかがわからない、というのが問題だよね。ネコは、人間の脳をおかす病気を持っていて、その病気にかかると人間はネコの中毒になってしまうという。そうなるんだよね? よくわからないけど、俺もその病気に感染していることはたしかだ(笑)。俺は初めて会ったときからネコが大好きだ。今回のアルバム・カヴァーの主役となったパーシーも大好きだ。ちょうどこのアルバムの制作に入るときに、子ネコのパーシーをもらってきたから、パーシーは今作に本質的に関連していたのさ。
■今回の新作はチック・チック・チックにとって8枚目のアルバムとなります。もうそろそろヴェテランの仲間入りと言ってもいいかと思うのですが、これまでの歩みを振り返ってみてどう思いますか?
NC:苦労の連続だったよ。でもこれは、つねに俺がやりたかったことなんだ。これに勝る重要なことはいままでに一度もなかった。他のバンド活動をしていたときも、アウト・ハッドを同時進行していたときも、このふたつのバンドは俺たちの子どもみたいなもので、両方ともいちばん大事だった。いままでずっと、この活動は、俺がいつもやりたいと思っていたことだから、あまり立ち止まって考えるということはしなかったね。俺がやってきたことは、つねに、バンドにとって最高のアルバムを次も出せるようにしてきた準備だった。チック・チック・チックというバンドの枠のなかで、俺たちがうまくなって、より良いバンドになっていくというのがつねに課題としてある。
■5枚目の『Thr!!!er』でパトリック・フォードとスプーンのジム・イーノをプロデューサーに迎えて、音が変わりました。その後パトリックとはずっと組んできて、今回も参加しています。彼のどういうところがあなたたちと合うのでしょう? ジムとの違いは?
NC:ジムは昔からいる典型的なプロデューサーという感じで、パトリックは新しいタイプのプロデューサーという感じだね。パトリックは単刀直入にものを言うから、俺たちをムカつかせるときもあるが、そこが俺たちと合っているんだと思う。でも冗談を言い合ったりできる関係性だから、彼は何かが良くないと「それは良くない」と言い、同時に俺たちのことをバカにできる。それは良いことだと思う。核心に触れることができるから。俺たちにたいしてなんでも言えるような人が欲しいからね。彼はその役に適している。パトリックは、俺たちが尊敬できるような、素晴らしい耳を持っている。それに彼とスタジオにいるのは楽しいから、彼と一緒に時間を過ごすのが俺たちはたんに好きなんだ。
■今作にはホーリー・ファックのグラハム・ウォルシュも多くプロデュースで参加していますね。彼が今回あなたたちにもたらしたものとは?
NC:グラハムはホーリー・ファックのメンバーで、そこで彼はホーリー・ファックのやり方で活動している。今回は彼がチック・チック・チックのメンバーとして何週間か加わったような感じだったからクールだった。だから俺たちとはちがうキャラクターやアイデアをバンドにもたらしてくれたよ。俺たちが提案しないようなことを提案してくれる人が好きなんだ。彼の活動しているシーンは俺たちと近いけれど、俺たちとはべつのことを提案してくれる人だったからそれが良かったな。

■“Couldn't Have Known”や“Domino”、“Rhythm Of The Gravity”などでは声が加工されたりチョップされたりしています。あなたたちの音楽において「声」はどのような位置を占めるのでしょう? 特別なものなのか、数あるサウンドのなかの1種類にすぎないのか。
NC:ヴォーカルは特別なものだと思うね。ヴォーカルは映画で言うとスクリーンの中央を占めているものだ。まわりでいろいろなことが起こっていて、メインとなるアクション。だが同時に、サウンドの1種類として扱うのも好きだ。俺たちが好きなダンス・チューンで聞こえるヴォーカルは、リズム楽器のように使われている場合が多い。そういう使い方も好きだね。だからヴォーカルでもなんでも、柔軟性を持って取り組むやり方が良いと思う。
■今後オートチューンを使う予定はありますか?
NC:過去に使ったことはあるよ。オートチューンは俺にとって、フルートやピアノと同じ、ひとつの楽器にすぎない。ピアノも、これから先のアルバム6作に使うかもしれないし、もう二度と使わないかもしれない。オートチューンもそれと同じ考え方だよ。
■“Serbia Drums”の上モノは80年代のポップスを想起させるのですが、それとは対照的にドラムが強烈です。歌詞もビジネスのダーティな側面を暗示させる内容ですが、なぜ「セルビア」なのでしょう?
NC:曲が、セルビアでおこなわれたサウンドチェックの音をもとに作られたからだよ。とても独特に響く空間で、ドラマーのクリス(・イーガン)が「この部屋の響き方は最高だ」と思い、あのビートをドラムで演奏して「これを使って曲にできないか?」と俺たちにファイルを送ってくれた。それは携帯電話で録ったビートだったんだけど、それを使ってラファエル(・コーエン)がこの曲にしたのさ。最初からこの曲は“Serbia Drums”というファイル名で、曲を完成させたときも、「それが曲名だな」と思った。ドラムの響きが特有なのを聴いてもらいたかったからこの曲名にしたというのもあるね。
西洋の世界において昔は、 聖書だけが人びとにとってのエンターテインメントだった。いまの時代はポップ・カルチャーやニュースがエンターテインメントになった。クレイジーな人たちはそれにインスピレイションを受けてクレイジーな行動に出ている。
■7曲目の“Slow Motion”からアルバムの雰囲気ががらりと変わり、“Domino”や“Rhythm Of The Gravity”と、いろんなタイプの曲が続きます。後半はかなりヴァラエティに富んでいると思うのですが、全体をこのような構成にした理由は?
NC:俺たちはアルバムを通しで聴くという世代の人間だ。最近はプレイリストなんかが人気で、音楽の聴き方が、アルバムよりも曲のほうが大事にされていて、シングルや45 rpmの時代に戻ったようで、それはそれでエキサイティングだと思うし、俺たちも気に入っているけれど、同時に俺たちはアルバムを聴いて育ってきた。だからアルバムをつくるというのは、俺たちにとっては夢が叶ったのと同じことだから、アルバムはリスナーが存分に体験できるものにしたいと思っている。映画のように山があり谷があり、サスペンスを感じる瞬間があるようにしたい。だから俺たちは、豊かで、バランスの良いアルバムを作ろうとしている。
■“$50 Million”は、「5万ドルでは僕の心は変えられない/でも、5000万ドル積めば変わるかも」「4900万ドルで手を打つ」というフレーズが印象的です。もし私が「4900万ドルあげるから、トランプ支持者になれ」と言ったら、なりますか?
NC:(爆笑)。たぶんならないだろうね。俺が寝返ると思ったかもしれないけど、俺はそんなことはしないよ。
■素朴に、お金は欲しいですか? ちなみに私は欲しいです。
NC:(爆笑)。いらないよ。ただバンド活動を続けられればいい。“$50 Million”は、「俺は絶対に寝返らないぜ」とやけに聖人ぶった感覚について歌っている曲で、寝返ったやつらを非難している内容なんだけど、同時に自分は絶対に寝返らない、とも言っている。だって絶対にもらえない額を提示しているからね。だから両方の意味があって俺は気に入っている。誰にでも、自分が手を打つ金額というものがある。歌詞にもあるけど、俺は誘惑されたこともあるけど、そんなに頻繁にじゃない。5万ドルでは俺の心は変えられない。
また、チック・チック・チックにとって「寝返る」ということがなんなのか俺にはよくわからない。俺たちはべつに寝返らない。自分たちに合わないと感じたCMの依頼は断ってきたけど、そんなに悪くないなと思ったCMの依頼は受けてきた。複雑で微妙なテーマではあるけれど、俺たちはまだ自分たちのパンクのルーツを主張して、そういう曲を書いてもいいと思っている。
■先週はテキサスとオハイオで立て続けに銃の乱射事件がありました。エルパソの方の事件は、移民にたいするヘイト・クライムだったとも言われています。トランプは自分は差別主義者ではないと言っているようですが、これはトランプが大統領になったことで引き起こされた事件だと思いますか? それとも彼はとくに関係なく、合衆国では以前からずっとそういうレイシズムにもとづく犯罪が多かった?
NC:その両方だと思う。レイシズムにもとづく犯罪はアメリカの歴史の一部として昔からあったことだ。だが、アメリカに住んでいる人なら誰でも明確に感じているのが、ここ数年でアメリカの雰囲気は変わったということ。レイシズムがアメリカに前からあったのはたしかだけど、トランプはそのレイシズムという火に油を注いでいる。その火をかき立てて、より大きなものにしている。あの乱射事件を起こしたやつは狂っていて、精神が病んでいることは間違いない。西洋の世界において昔は、 聖書だけが人びとにとってのエンターテインメントだったから、それをもとにクレイジーなことをするやつがいた。クレイジーなヴィジョンを持って、それをやる必要があると思って実行するやつがいた。いまの時代には、クレイジーなことをするためのインスピレイション源が聖書以外にもたくさんある。ポップ・カルチャーやニュース、そういうものが人びとのエンターテインメントになった。クレイジーな人たちはそういうものにインスピレイションを受けてクレイジーな行動に出ている。
■アルバム・タイトルの『Wallop』には、そういう暗い状況を打ちのめしたい、という想いが込められているのでしょうか?
NC:もちろんだよ。タイトルにはいろいろな意味があるんだけど、「Wallop」という言葉を調べたときに、まずはその言葉じたいに惹かれた。「なんておもしろい言葉だろう!」と思った。少し古臭い言葉で、最近はあまり使われない。でも使うときは、独特な意味を持って使う。「Wallop」という特有の打たれ方として使う。調べたら、「簡潔明瞭で、相手を驚かせる打ち方」とあった。このアルバムも簡潔明瞭に響くものにしたかった。そして驚かせるようなパンチのあるものにもしたかった。前回の大統領選挙では、共和党からびっくりするようなパンチをくらった気がした。俺たちはみんな驚いたよ。このアルバムは俺たちの反撃を意味している。俺たちもやつらにたいして「Wallop」をお見舞いしたいと思ったんだ。
ジェントリフィケイションは悪で、俺たちはそれを嫌っているけど、同時にジェントリフィケイションによって治安は良くなるし、街もきれいになる。だからどういう意見を持つべきなのか、よくわからなくなる。
■いまオカシオ=コルテスの名が日本でも広まってきていますが、やはりすでに合衆国では多くの支持を集めているのでしょうか? まわりのアーティストたちの反応はどうですか?
NC:彼女はアイコン的人物になりつつあるよ。いままで民主党があまり上手にはやってこなかったことを彼女はやれていると思う。トランプがヒラリーに勝利したのは、トランプのほうが芸能人として上だったからだと俺は思っている。トランプのほうが、人びとの想像力を掻き立てるのがうまかったんだ。トランプの方がヒラリーより興味深い人物だとみんなは思ったんだろう。民主党は、人びとが共感できないような人ばかりを候補者に立てている。だが、人びとはオカシオ=コルテスのことを英雄のように見ている。彼女にたいしては、多くの人が強い共感を持てて、インスピレイションを感じることができる。それはエキサイティングなことだ。彼女は過激なヴィジョンを持っていて、俺は個人的にそこが好きで魅力を感じる。でも彼女が人気である理由は、彼女の気の強い性格と、早い対応や、いまの時代に合っているというところだと思う。
■10曲目の“Domino”は今回のアルバムのなかでもとくに異色です。IDMっぽくもありますし、昔の電子音楽のようでもあり、どこか子ども向けの音楽のような雰囲気もあります。なぜこのような曲を入れようと思ったのでしょうか?
NC:俺たちはつねにちがうスタイルの音楽をつくってみたいと思うし、いろんなものからインスピレイションを得ている。この曲は、さまざまなパーツが徐々に集まっていってできあがった。ラファエルはキーボードでフルートの音を出して実験していて、「このフルートの音でどうやって曲を作るんだろう?」って言って、あのメロディの部分を俺に送ってくれた。それを聴いて、ビートなどを加えたりしていじっていたら、そこに遊び心を感じた。それがドミノみたいだと思った。そこから「ドミノ・シュガー」という砂糖会社の工場を連想して、ここ15年間、その工場がブルックリンで物議を醸していることを思い出した。そこには嬉しさと悲しさが同時に感じられた。そして遊び心も。まるであの砂糖のパッケージを見たときに感じるように。ドミノ・シュガーの、黄色い紙パック。それはセンティメンタルな気持ちと悲劇の両方を感じさせる。ドミノ・シュガーの象徴だった工場、そしてブルックリンの象徴だった工場が消えてしまったんだ。
■歌詞にある「1917年の工場」というのがそれですか?
NC:(笑)。俺たちは、じっさいの曲に入りきらないくらいの歌詞を書いていたんだ。言いたいことがたくさんあったからね。リリック・シートを提出するときに、思いついた歌詞のすべてを気に入っていたから、ぜんぶ提出した。「1917年の工場」の部分は、曲では歌われていない部分なんだけど、気に入っているから残した。当時の事件をウィキペディアで調べたんだけど、あの歌詞の部分は、ほぼウィキペディアからの受け売りだよ。でもあの文章は、ブルックリンで物事が変化していく様子を、うまく捉えていると思ったから引用した。1917年に工場で火災が発生したとき、5万人が、工場が燃え尽きるのを見物していたという。それがすごく魅惑的なイメージだと思った。その瞬間のエンターテインメントはそれだったんだよ。テレビより前の時代、映画が生まれて間もないころ、人びとはストリートに出て、出来事を見物していた。ニューヨーカーたちが巨大な火災を見物して、砂糖工場が崩壊するのを見ている、というシーンを想像するのが楽しかった。とてもパワフルなイメージだったから、歌詞として残したいと思った。俺たちが現在見ている景色を象徴していると思ったから。
■その出来事がドミノのように、現在まで繋がっていると。
NC:もちろんあるよ。物事が倒れて、変化していくという意味だから。それは、原因と結果という自然なことなのかもしれないし、自然現象なのかもしれない。ただ遊び心があるだけなのかもしれない。
■いま東京はオリンピックのせいで再開発が尋常ではないペースで進み、数週間単位で道が変わったりしているところもあるのですが、この曲はジェントリフィケイションの問題とも関係しているのでしょうか?
NC:そうだね。でもこの曲では、ジェントリフィケイションにたいして批判しているわけではないんだ。ただ、そういう変化に混乱している、と歌っている。工場は資本主義を意味する。資本主義の象徴だったものが、「公園」という人びとの象徴になるというのは、フェアじゃないかもしれない。クソみたいな工場だったから、閉鎖されて当たり前だったかもしれない。このような土地開発が意味することはすべてを理解できない、という意味合いの内容なんだ。ジェントリフィケイションは悪で、俺たちはそれを嫌っているけど、同時にジェントリフィケイションによって治安は良くなるし、街もきれいになる。だからどういう意見を持つべきなのか、よくわからなくなる。

人びとが集まり、考えを共有する。孤立していた人たち同士が、互いを見つける。ダンス・ミュージックには今後もそうであってほしい。
■今回のアルバムを作るうえで、とくに意識したり参照したりしたアーティストや作品はありますか?
NC:今回のアルバムのインスピレイションとなった音楽のプレイリストを今度出す予定だけど、俺たちは聴くものすべてにいつも影響されているし、新しい音楽をつねに聴いている。じっさいに新しい音楽と、俺たちにとって新しい音楽という意味でね。でも今回のアルバムはほか作品と比べると、さまざまな機材に影響を受け、その機材を使っているうちに発見したことなんかがインスピレイションのもとになっている。
■今年は〈Warp〉の30周年です。あなたたちが契約してからおよそ15年が経ちますけれど、あなたから見てレーベルの変わったところと、逆に変わっていないところを教えてください。
NC:変わっていないのは、エキサイティングで新しいと感じる作品をリリースし続けている点だと思う。俺たちが〈Warp〉と契約したとき、〈Warp〉はIDMから離れはじめていて、それは俺も変だなと思ったけれど、IDMは当時、勢いがなくなってきていて、あまりおもしろいものではなくなっていた。俺たちのほうが、よりおもしろいグループだった。〈Warp〉は、古いIDMのような音楽ばかりを出しているレーベルではなく、おもしろくて、新しいグループと契約するレーベルなところが良い。 だってIDMは、同じことを繰り返しやっていたら、インテリジェントじゃないだろ? 〈Warp〉は新しい音楽に傾倒しているからそれはエキサイティングだと思う。
■では変わったところは?
NC:レコード業界全体が変わったから、その影響で変わった点はある。アルバムをリリースするたびに、レコード業界は変わっていく。今回リリースするアルバムのためには何をしないといけないんだろう、と考える。マイスペースでこれをやって……とか、そういうトゥールが毎回ちがったりする。だから、〈Warp〉の何が具体的に変わったかというのを答えるのは難しいけれど、レコード業界が変わったからその変化が〈Warp〉にも反映されたとは思う。〈Warp〉の反映のさせ方は間違っていなかったと思うよ。俺たちが初期に関わっていたレーベルの多くはもう店じまいしてしまったからね。その一方で〈Warp〉は、いまでも時代を先どりして新しい音楽をリリースし続けているしね。
■〈Warp〉のタイトルでベストだと思う作品を3つ挙げるなら?
NC:おもしろいことに、俺たちにもっとも影響を与えたのは、〈Warp〉が10周年を記念してリリースした『Warp 10: Influences, Classics, Remixes』だった。俺たちは当時、ダフト・パンクや初期のシカゴ・ハウスなんかを知ったばかりで、それまではエレクトロニックな音楽やハウス・ミュージックをいっさい知らなかった。だから、あのアルバムが出たときはいつもそれを聴いていたよ。あのアルバムがハウス・ミュージックを知るきっかけになった。
それから、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの『R Plus Seven』。あのアルバムは大好きだね。俺がよく聴くアルバムだ。彼はとてもユニークなことをあの作品でやったと思うし、アルバムを聴いて、その世界に迷い込むことができる。すごく気に入っているアルバムだよ。
あとは、オウテカの「Peel Session」。俺たちがまだサクラメントに住んでいた初期に、俺たちが所有している数少ないエレクトロニック・ミュージックのレコードだった。すごく大好きで何回も聴いていたね。
■NTS で放送された〈Warp〉30周年の番組で、チック・チック・チックは「Why Can't All DJs be as Exc!!!ting as Nic & Mario?」というミックスを提供していましたよね。とにかくずっとダンサブルな曲が続くミックスでしたが、最近もっとも打ちのめされた曲を教えてください。
NC:最近は、スワンズをたくさん聴いているね。最近もっとも打ちのめされた曲の名前は“In My Garden”だよ(註:1987年のアルバム『Children Of God』に収録)。
■あなたたちの音楽はとにかくダンスを忘れません。それは2000年のファースト・アルバムのころからそうですし、ヴァラエティに富んだ今回のアルバムでもそうです。なぜ私たちにはダンスというものが必要なのでしょう? それは人間にとってどのような意味を持つのでしょうか?
NC:ヴィヴィアン・ウェストウッドのインタヴューを読んでいたとき、彼女はパンクについて文句を言っていて、こんなことを言っていた。「パンクは、ただみんなが集まって走り回るための口実だった」と。それは馬鹿げた見方だなと思ったよ。だって、それこそが、すべての芸術運動のエキサイティングなところだと思うから。人びとが集まり、考えを共有する。いままでは孤立していたかもしれない人たちが、似たような考えの人たちと集まる。ダンス・ミュージックには、そのようなアンダーグランドとの繋がりがつねにあったと思う。孤立していた人たち同士が、互いを見つける。ダンス・ミュージックには今後もそうであってほしい。人びとが集まる方法のひとつとしてね。
■あなたにとって史上最高のダンス・レコードを教えてください。
NC:ザップの「More Bounce To The Ounce」だね。
!!! - WALLOP JAPAN TOUR -
東京公演:2019年11月1日(金) O-EAST
OPEN 18:00 / START 19:00
前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
主催:SHIBUYA TELEVISION
INFO:BEATINK 03-5768-1277 / www.beatink.com
京都公演:2019年10月30日(水) METRO
OPEN 19:00 / START 20:00
前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
INFO:METRO 075-752-2787 / info@metro.ne.jp / www.metro.ne.jp
大阪公演:2019年10月31日(木) LIVE HOUSE ANIMA
OPEN 18:00 / START 19:00
前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
INFO:SMASH WEST 06-6535-5569 / smash-jpn.com
[チケット詳細]
一般発売:7月13日(土)~
東京公演:
[先行発売]
★主催者WEB先行:6/19 (水) 23:00~ [https://beatink.zaiko.io/_item/315726]
★イープラス最速先行(抽選):6/25 (火) 正午12:00〜6/30 (日) 18:00 [https://eplus.jp/chkchkchk/]
★ローチケ・プレリクエスト(抽選):7/2 (火) 12:00〜7/7 (日) 23:00 [https://l-tike.com/chkchkchk]
★イープラス・プレオーダー:7/5 (金) 12:00〜7/8 (月) 18:00
〈チケット取扱い〉
イープラス [https://eplus.jp/chkchkchk/]
ローソンチケット (Lコード:75346) [https://l-tike.com/chkchkchk]
Beatink [https://beatink.zaiko.io/_item/315726]
チケットぴあ(P: 156-986) [https://t.pia.jp]
iFLYER [iflyer.tv]
京都公演:
[先行発売]
★主催者WEB先行:6/19 (水) 23:00〜 [https://beatink.zaiko.io/_item/315730]
★イープラス最速先行(抽選):6/25 (火) 正午12:00〜6/30 (日) 18:00 [https://eplus.jp/chkchkchk/]
★ローチケ・プレリクエスト(抽選):7/2 (火) 12:00〜7/7 (日) 23:00 [https://l-tike.com/chkchkchk]
★イープラス・先着プレ:7/5 (金) 12:00〜7/8 (月) 18:00
〈チケット取扱い〉
イープラス [https://eplus.jp/chkchkchk/]
ローソンチケット 0570-084-003 [https://l-tike.com/]
チケットぴあ [https://t.pia.jp]
大阪公演:
[先行発売]
★主催者先行受付(抽選):6/25 (火) 12:00〜7/1 (月) 18:00 [https://eplus.jp/chkchkchk/]
★イープラス・プレオーダー:7/5 (金) 12:00〜7/7 (日) 23:59 [https://eplus.jp/chkchkchk/]
〈チケット取扱い〉
イープラス [https://eplus.jp/chkchkchk/]
ぴあ (P: 156-408) / 英語販売あり
ローソン (L: 54243)
iFLYER
企画・制作:BEATINK / https://www.beatink.com